「硬筆書写技能検定を初めて受けるんだけど、何の本を買ったらいい?どういう道具を揃えたらいい?」という質問をされたことがあるので、最初にやっておいた方が良いと思うことをまとめてみました。
◆何級から受験するのが良い?
→これは現時点での筆力にもよりけりですが、私は3級から受験しました。(※3級受験時点での年齢は38歳でした)
何故3級から受験したのかというと、3級受験の時点で「3級なら少し練習すれば今の自分でも受かりそう」だと思ったからです。
4級はさすがに簡単すぎるし、2級はハードルが高すぎる。
(※2018年1月時点ではまだ準2級がなかった&2級の理論問題がオール記述式だったので、理論も結構難しそうに感じた)
もっとも、書道教室に通い始めたのは2017年6月で、硬筆3級を受験したのが2018年1月だったので、硬筆は3級くらいがちょうどよいと思ったのですが、これがもし2020年以降に「硬筆書写・毛筆書写技能検定を受けてみよう」と思い立っていたら、準2級からスタートしていたかもしれないです。
※2020年(平成30年度第1階試験)より、3級・準2級・2級の理論はマークシート方式に変わった。
あまりに簡単すぎても、難しすぎてもモチベーションの維持が難しい。
ですので、まずは書写技能検定がどんな試験なのかを体験するという意味でも、「この程度なら少し練習すれば受かりそう」と思えるレベルからスタートするのがちょうど良いと思います。
大まかな目安としては、小学校低学年だったら6級、小学校中学年なら5級、小学校高学年なら4級か5級、中高校生なら3級か4級、大学生・一般の方なら3級~2級あたりから始めるのが良いのではないでしょうか。
参考サイト:日本書写技能検定協会 問題例と解答例
◆最初は何を買ったらいい?
仮に硬筆3級から受験をするとしたら…
過去問(試験傾向の把握のため)
◎最新版の「硬筆書写検定3級 合格のポイント」(日本習字普及協会)
○硬筆書写技能検定の手びきと問題集(2019年版・楽天kobo版)
△日本書写技能検定協会で買える過去問題(1回分・3回分)
ペン字練習帖(基礎練習用として)
○硬筆書写3級のドリル(日本書写技能検定)
○大人が学ぶ小学校の漢字(二玄社)
○きれいな文字の書き方(二玄社)
書体字典
○常用漢字書き方字典(二玄社)
など、楷行草三体が収録されている書体字典を最低1冊用意する
筆記用具類
・ボールペン(第1問速書き用、第2問~第5問用)
・油性マーカー(第6問掲示文用)
・30〜40cmの定規(第6問掲示文用)
・鉛筆と消しゴム(第6問掲示文用、理論問題用)
・本番と同じ紙質の練習用紙(日本書写技能検定)
・廉価な国語ノートまたはA4のコピー用紙
・ソフト下敷き
まず、最新版の「硬筆書写検定3級 合格のポイント」をお勧めしたいです。
これはamazonや楽天、書道用品店などで買えます。
この1冊には、直近の過去問6回分と、各問題ごとの出題例や答案作成のポイント、理論問題、漢字の筆順、部首の名称など、3級合格に必要なことが過不足なく網羅されています。
ですので、これは絶対に買ったほうがいい。
もし本試験まで時間がないような状況でしたら、最低でもこの1冊だけは繰り返し練習した方が良いと思うくらいです。
楽天kobo版の「硬筆書写技能検定の手びきと問題集(2019年版)」は、楽天koboアプリをスマホやipadに入れて読めます。
こちらの本は平成29年・平成30年の1~5級までの過去問がそれぞれ6回分収録されているので、更に過去問類題の演習をしたい人や、今後3級から準2級・2級・準1級・1級へとステップアップしたい方は買った方がいいと思います。
日本書写技能検定協会でも、直近の過去問1回分と、前年度の過去問3回分を購入することができます。
毛筆の場合は協会で買える過去問は必須ですが、硬筆は「合格のポイント」が毎年改訂されるので、協会で過去問を購入するメリットはあまりないかもしれません。
ただ、協会で過去問を買うと、答案の作成例(採点の上限と下限例)がついてくるので、どの程度書けたら合格ラインをクリアできるかの参考になると思います。
ペン字練習帖としては、
試験の出題傾向に添った類題の練習をしたい人は「硬筆書写3級のドリル」
楷書・行書・草書の点画を基礎からきちんと練習したい人は「大人が学ぶ小学校の漢字」「きれいな文字の書き方」の2冊がお勧めです。
硬筆3級を受験するだけなら、「硬筆書写3級のドリル」の1冊があれば足りると思います。
ですが、今後準2級・2級・準1級・1級へのステップアップを考えているのでしたら、「大人が学ぶ小学校の漢字」「きれいな文字の書き方」の2冊を持っていても損はしないと思います。
まず字形に癖がなくて綺麗ですし、筆者の先生は書写技能検定協会の理事も務めているので、少なくともこの練習帖にある字形で答案を書けば減点されることがないであろう安心感があります。
楷書・行書・草書の三体が収録されていますから、3級だけでなく、準2級・2級・準1級・1級まで長く使えます。
書体字典については、「大人が学ぶ小学校の漢字」と筆者が同じである「常用漢字書き方字典」が一冊あると便利です。
これも、一度買ったら1級まで長く使えますから、2~3級を受験する段階で買っておいたほうがいいでしょう。
(一時期、版元ですら注文を受け付けておらず、中古本の価格が異常に高騰していましたが、2023年現在、amazonなどで普通に購入できるようになりました。)
筆記用具類について。
私は3級~2級までは万年筆カクノとかSARASAなどを試していましたが、硬筆1級・準1級の時点で
第1問(速書き)はジェットストリームかドクターグリップの0.7㎜
第2~第5問はエナージェル0.7㎜
第6問(掲示文)はコピックチャオ(黒)
に落ち着きました。
個人的には、替え芯の入手のしやすさ・値段を考えると、
第1問は三菱鉛筆 油性ボールペンジェットストリームの0.5㎜か0.7mm
第2~第5問はぺんてる ゲルインキボールペン エナージェル0.7㎜
第6問はコピック(コピック チャオ ブラック)・プロッキー(三菱鉛筆)・マッキー(ゼブラ)のどれかを買うと良いと思います。
ジェットストリームは、値段自体もそれほど高くなく、コンビニや100均でも買えること。書き心地も良い。
エナージェルは、書き心地も良いですが、インクの渇きが速いので、答案用紙を汚す心配が少なくて済むのが良いところです。
芯の太さはそれぞれ好みがあると思いますが、私は0.7mmがちょうど良いかなと思っています。細すぎるとよっぽど筆圧の強い人じゃない限り、なんとなく頼りない線に見えてしまうんですね。細かい字を書くわけではないので、最低でも0.5mmはあった方が良いと思います。
第6問はコピック一択ではないのは、コピックは慣れると変化にとんだ線が書けるものの、ある程度大きい文具店にしか売ってないこと、インクの交換が少し面倒(そのくせインクの消費量が速い)なのが、やや扱いにくいと思うからです。
コピック・プロッキー・マッキーの3本を買ってみて、書きやすい・解答用紙の見栄えが良いと思ったペンを使うのが良いと思います。
練習で使う紙類・ノート。
・本番と同じ紙質の練習用紙(日本書写技能検定)
・廉価なノートまたは自作の練習用紙
私は字形を覚える時(特に草書体のインプットの段階)は廉価なノートまたはコピー用紙(自作の練習用紙)で、ある程度書き慣れたら、本番と同じ紙質の練習用紙を使って練習するようにしていました。
普通の紙やノートに比べると若干高いかもしれないのですが、検定用の練習用紙の購入はあまりケチらない方が良いと思います。
最初から最後まで練習用紙を使う必要はないですが、試験の直前になったら使い慣れておいた方が良い、ということです。
練習用のノートには、小学生が使うような「かんじれんしゅうちょう」「こくごノート」「じゆうちょう」を使っていました。
何故かというと、漢字や国語のノートは右綴じになっているので縦書きに対応していること、またマス目が入っているので、字の練習にちょうど良いからです。
とはいっても、大の大人が小学生用の国語ノートを使うのはちょっと…と抵抗を感じてしまう方もいるかもしれません。
(デザインがいかにも小学生向きだからね)
そういうのが嫌な方は、無印良品の「学習帳 5mm方眼」や「学習帳 こくご 12マス」がシンプルで使いやすいと思います。



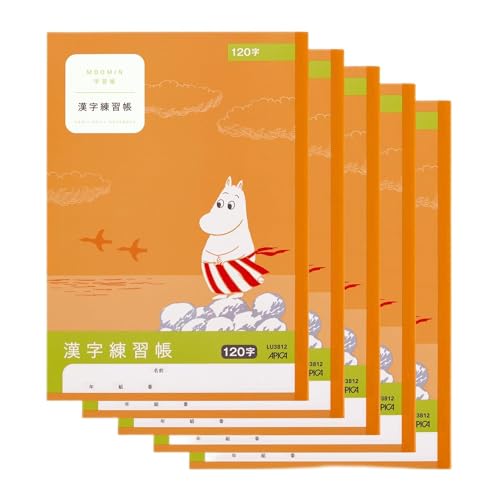



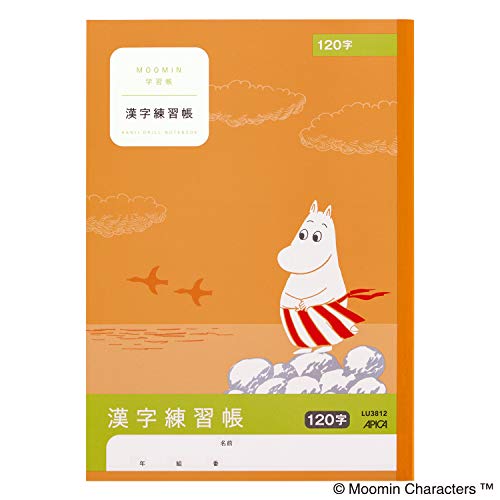





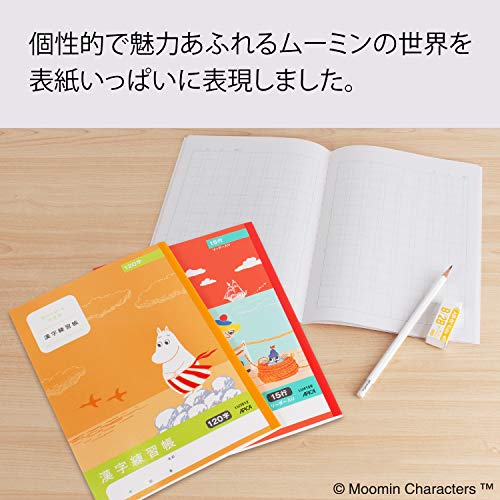


コメント
硬筆準1級が、なかなか合格できずこのサイトを見つけました。毎日、何時間練習しましたか?何を練習しましたか?
みちこさん
使用した本はこの記事に書いたので参考にどうぞ↓
この時は毛筆準1級と併願、毎日展の作品制作もあったので、硬筆対策に何時間練習していたかは覚えていませんが、草書を覚えるのに大半を費やしていた気がします。
miwaさんからの返信感激です。
やっぱり毎日ペンを持っていたんですね。字形にチェックがつく場合、miwaさんなら、どんな勉強をされますか?
>字形にチェックがつく場合、miwaさんなら、どんな勉強をされますか?
字形のチェックといっても、楷書・行書・草書・平仮名のどれにチェックが入るかにもよりますが、市販のペン字練習帖(大人がまなぶ小学校の漢字など)を使った基礎点画の練習に戻ります。
準1級、理論は合格しているのですが、実技がなかなか合格できず悩んでいます。
何を勉強したらいいのか…
第3問は、必ず字形にチェックが付きます。線質にチェックもついたりします。
第5問6問は、構成にチェック付くときがあります。模擬テストでは、合格点に5点〜10点足りない結果で、本番までに練習しているつもりです。勉強の仕方、時間の使い方を教えてください。
第5問は漢字/近代詩文/仮名のどれを選択しているかにもよりますが、第5問・6問で構成を指摘されるのは、字の大きさや天地左右の余白の取り方の改善が必要かもしれません。
他の問題は回答用紙に罫線が入ってるからその枠内で書けばいいですが、この問題は白紙に回答を書くわけですから。
これは書写技能検定協会で買える練習用紙でもって練習するのがいいかなと思います。(コピーして使いまわしてもOK)
第3問で字形に必ずチェックが入るとのことですが、私なら、「大人が学ぶ小学校の漢字」「きれいな文字の書きかた」をもう一度復習しますね。なんなら手本の綺麗な文字をそっくり真似する、くらいやってみてもいいかもしれない。
練習時間は、あまりまとまった時間が取れなかったので、朝出勤前に30分~1時間、夜習い事から帰ってきてから30分~1時間みたいな感じでやってましたよ。
大人が学ぶ小学校の漢字ときれいな文字の書き方を注文しました。おすすめの辞書、高いですね?
第5問、漢字を今回初めて挑戦して構成にチェックが付きました。今までは、現代詩を選択してきましたが、その時は字形にチェックが付いていました。第3問の行書縦書きもチェックが付くから、行書がダメ?ひらがな?毎日、ひらがなを書くようにしています。
質問攻めですが、速書きは手が震えましたか?
みちこさん
確かに書体字典はちょっとお高めなので無理にとは言わないですが、書写技能検定で合格できる字形という意味で、最低一冊買うとしたらまずはこの「常用漢字書きかた字典」をお勧めしたいですね。
準1級の漢詩は10文字なので、縦2列5文字ずつ、漢字をある程度大きめに書いて、天地左右の余白を均等にとればよいと思います。
(私は練習の段階で鉛筆の枠線を書いた紙をコピーして使いまわしてました)
字形にチェックが入るということは、やっぱり行書体の字形が合格基準点に届いていないのかなと思われます。
あと平仮名が行書とマッチしていないか。行書に調和する平仮名や連綿は「きれいな文字の書き方」に収録されていますから、参考に練習してみた方がよいと思います。
速書きは多分みんな手が震えると思うけど、これは普段の練習で、過去問をタイムを計測しながら練習して、3分~3分30秒で書けるようにしておく。そうすれば本番は多少緊張していても4分以内に全部書ききれると思います。
書体辞典、購入しました。確かに役に立ちそうです。
miwaさんなら、第5問の漢字の枠の大きさは、どれくらいにしますか?
第3問、連綿は使いましたか?
質問ばかりでゴメンなさい。独学で、準1級合格するのは難しい…
第3問は連綿を使いましたが、せいぜい2~3か所程度でしたよ。
過度な連綿は求められていないので、入れられるところにちょこっと入れる、くらいで大丈夫です。
第5問の漢字の枠の大きさは、たしか横10センチ・縦17~18センチか、そのくらいだったと思います。
先に鉛筆で枠を書いてしまって、その中で10字を書いていました。
(第5問回答用紙のサイズは縦25.7cm、横16.2cm)
第5問、枠はだいたいmiwaさんと同じくらいです。行書と草書をまぜて書いた方がいいのか、行書だけで書いた方がいいのでしょうか?
草書を覚えてない字もあります。
診断テスト結構、来ました。やはり5点足りずでした。
第5問の漢字は行草ではなく、行書のみ、または楷書で書いてみてはどうでしょうか。
私は準1級のときは行書と草書を半々くらいで書いてましたが、1級では楷書で書いてました。
(硬筆で行草体を書いても今一つしっくりこなかったので、行書や草書の字形で減点されるリスクを減らすために、楷書に切り替えた経緯あり。)
準1級はどの科目も評価4が取れていないと合格ラインがクリアできないので、どの科目も4または5が取れるような練習が必要という意味では、地味に大変だと思います。
1級だと評価4が4つ、評価3が2つでもギリギリ合格できるんですがね(もちろん準1級よりも評価は厳しいですよ…準1級では5だったものが1級では3~4になる、という感じなので)