
今日の午前は、日本書道専門学校にて、硬筆書写技能検定準2級を受験してきました。
え?準2級?と思われる方もいるかもしれませんが、平成30年度(2018年第1回試験)より、準2級と6級が新設されました。
準2級の難易度は、「高校生・大学生・一般社会人程度(硬筆書写のやや専門的な技術及び知識をもって書くことができる。)」となっています。
午前は硬筆書写、午後は毛筆書写の検定がそれぞれ実施されるので、硬筆の中で2級と準2級、というような併願受験はできません。
ただし、毛筆3級と硬筆3級のように、毛筆と硬筆を併願することはできます(昨年はそれで硬筆3級と毛筆4級をダブルで受験したのだが、併願で受験している人は、下位級では私以外にはいなかった…。)
ちなみに今回は、毛筆との併願ではなく、硬筆のみを受験しました。
(毛筆3級はもう少し行書が上手になったら受験します)
さて硬筆書写検定の教室。
今回は、2級と準2級の受験者が集められていました。
2級は20人、準2級は16人いました。
女性が約8割超だったものの、年齢層は割と幅広かったと思います。
少なくとも、昨年毛筆4級を受けた時のように、周りが小中高校生ばかりで肩身がせまいということはなかったです。
会場は書道の専門学校だけあってか、教室の後ろには水道があったり、ロッカーの上にはデカい条幅(二八用?)の毛氈が置かれていたりしていました。
あと、受験票にはスリッパ持参とありましたが、今回は特に必要はなかったみたいです。
集合時間は試験開始時間の20分前となっていたけど、実際には試験開始時間(10時)から説明・問題用紙・マークシートの配布が行われました。
準2級の試験内容
準2級・2級の試験時間は90分です。
※硬筆書写技能検定は問題用紙を持ち帰ることはできません。
なので、過去問を例に、出題形式の説明をしたいと思います。
まず最初に、実技第1問目の「速書き」を一斉に実施します。
準2級は約130文字を書きます。

1分間の黙読→4分以内で筆記→5分で解答の回収・確認を行います。
(準2級は約 語程度・5行程度の文章を書きます)
この問題は、ボールペンで解答します。
残りの85分で、第2問~第6問(実技)、第7問〜第10問(理論)を解くことになります。
第1問目の速書き課題が終了した以降は、どの順番で問題を解いても構いません。
第2問目は「漢字10字を書く(楷書・行書)」です。

これは3級と同様、マス目にあわせて、漢字2字の熟語を楷書・行書でそれぞれ書きます。
第2問目〜第5問目までは、ボールペン・サインペン・万年筆などで解答をします。
第3問目は「縦書き」です。

約4行程度の文章を、縦書きで書きます。
漢字は行書指定ですが、ひらがなは連綿で書いてもよい、となっています。
(2級と同じです)
第4問目は「横書き」です。

約6行程度の文章を、横書きで書きます。
漢字は楷書指定ですが、数字・ローマ字については特に指定はありません(漢字に合っていればOK)。
字数は2~3級の中間くらいです。
第5問目は、「はがきの本文」です。

3級では「はがきの表面(住所・宛名・差出人)」を書く問題でしたが、準2級では「はがきの本文(縦書きの文章)」を書く問題が出題されます。
(2級と同じ出題形式です)
字体については特に指定はありませんが、「縦書きで体裁よく書くこと」となっています。
あくまでハガキの裏面ということを考慮すると、草書で書くと、受け取った人がかなりの確率で読めないだろうから、漢字は行書体がちょうどよいのではないかと思います。
また、余白が余りすぎないようにする、字の大きさのバランスを整える、行頭をそろえる、縦の列をまっすぐにする(字の中心線を通す)などの、レイアウトを考えて書く必要があります。
第6問目は「掲示文」です。

B4の普通紙に、油性マーカーor耐水性顔料のマーカー(先が1.5〜2ミリ)で、掲示文を書きます。
これは2級・3級とも同じ課題です。
ただし3級のほうが、レイアウトが組みやすい文字数で出題されていたと思います。
字体についての指定はありませんが、「縦長・横書きで、体裁よく書くこと」とされています。
掲示文の課題は、定規・鉛筆で文字配置のレイアウトを組むことは認められていますが、文字を下書きするのは不可です。
レイアウトの線・マルなどの下書き鉛筆線は、すべて消して提出します。
※定規と鉛筆でレイアウトを組んでもよいのは第6問目の掲示文のみで、第5問のハガキ文などではレイアウトを組むことは認められていません。
なお、B4の回答用紙とは別に、白紙が1枚配られます。
(薄い上質紙に油性ペンで字を書くので、下に何も敷かないと、机にインクが裏移りしてしまいます)これを下敷きとして使用します。
理論問題はマークシートの択一式・○×形式で出題されます。
なので、鉛筆orシャープペンシルで解答します。
第7問は「常用漢字の楷書と行書の筆順」が10問出題されます。
書き順が正しいものは○、間違っているものは×をマークします。
3級では10問とも楷書の書き順問題でしたが、準2級では、楷書と行書が5問ずつ出題されます。
第8問が「草書を熟語で読む」
草書でかかれた熟語を、常用漢字(楷書)の4択から選ぶ問題が、10問出題されます。
行書っぽい書体もあれば、元の字が何なのか一見するとわからない漢字もあり、1〜2問ほど迷いました。
第9問目(A)は「文字の歴史」
あ→安 か→加 け→計 など、ひらがなのもとになっている漢字を、4択の中から選びます。
これが5問でます。
なお、準2級では、変体仮名は出ません。
いろは仮名のみです。
書道教室で仮名の練習をしておいてよかった~w
第9問目(B)は、「漢字の部分の名称」
漢字のへん・つくりなどの名称を、4択から選ぶ問題が5問出ます。
これは3級と同じですが、3級よりもやや難しいものが出題されます。
第10問目は、「漢字の字体」です。
常用漢字の字体からみて正しい漢字には○、間違っているものには×をつけます。
20問出題されます。
1問目の速書きを終えた後は、まずは理論の第7問〜第10問を先に解いてしまい、残り時間で実技をゆっくりと書きあげました。
とはいっても、実際には30〜40分くらい残して退室しちゃいましたが。
2級ならともかく、準2級では90分もいらないような気がします。
あと、昨年3級を受けたときは、確か実技の問題用紙と理論の解答は同じだったのですが、今年度からは理論問題はマークシートでの回答に変わったようです。
ああ、だから4択問題と○×問題に変わったのですね。
(以前は答えを紙に直接書いていました。)
記述からマークシートに変わったことで、理論問題は昨年度よりも多少解きやすくなったのではないかと思います。
感触としては、理論は多分合格点が取れているはずです。
実技は…どうだろう?
トータルで75点%以上得点できているか?というと、自信をもって大丈夫とはいいがたい。
楷書はそこそこ書けているとは思うけど、行書はやっぱりまだ書き慣れていないんですよねー。
お手本があればそこそこ?書けるけど、お手本なしで自運というのはなかなか難しいですね(*´Д`*)
準2級は新しくできた級ということもあってか、準2級専用の対策問題集というのはなくて、手がかりになるものは過去問題だけ。
過去問と実際に本試験を解いた感じからすると、試験問題の構成は2級寄りで、2級を少し易しくした程度のレベルと感じました。
なので、理論のみの合格か、両方とも合格しているかのどちらか…ですかね。
もちろん両方合格していてほしいですけども。














































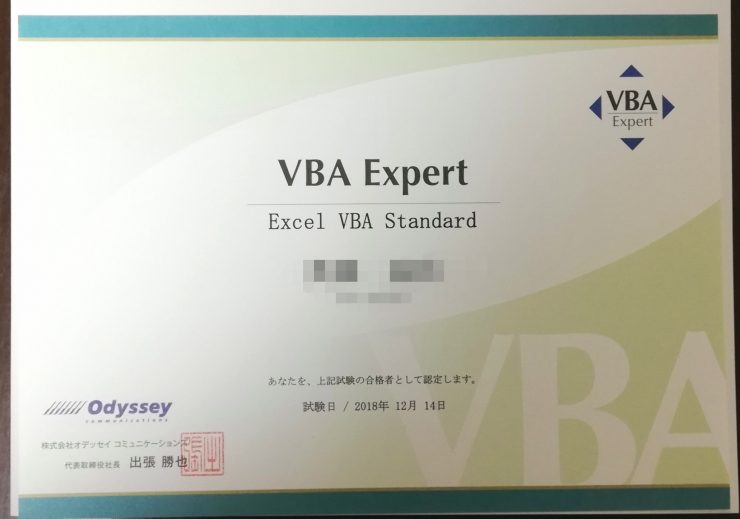
コメント
たまたまですが、同じ試験会場で受けていました。(私は2級です)
合格されていますように☆
>あやさん
まぁ!同じ会場にいらしたのですね。
合格は…どうかなぁ。理論のみ合格か、両方合格かのどっちかかな〜〜っていう手応えです。もちろん受かっていてほしいですけども。
初めまして
来年1月の硬筆書写技能検定試験準2級を受験する予定ですが、2点質問させて下さい
先ずひとつ目
掲示文の問題で、文字部分、余白部分のスペースを考えるのに、本番に向け定規で線を引く練習をしておいた方がいいですか?
ふたつ目
理論と実技両方共合格ラインを超えて初めて準二級が合格となりますよね?
宜しくお願いします
研城さん
初めまして、コメントありがとうございます。
掲示文課題は、定規をひく→文字を書く→消しゴムをかける の練習を毎回やるのは面倒臭いので、普段は線を引いた練習用紙をコピーして使いまわしてました。
直前期だけ、本番を想定した練習をやってましたね。
準2は、硬筆・実技にそれぞれ合格基準点があるので、両方合格して準2級合格になります。